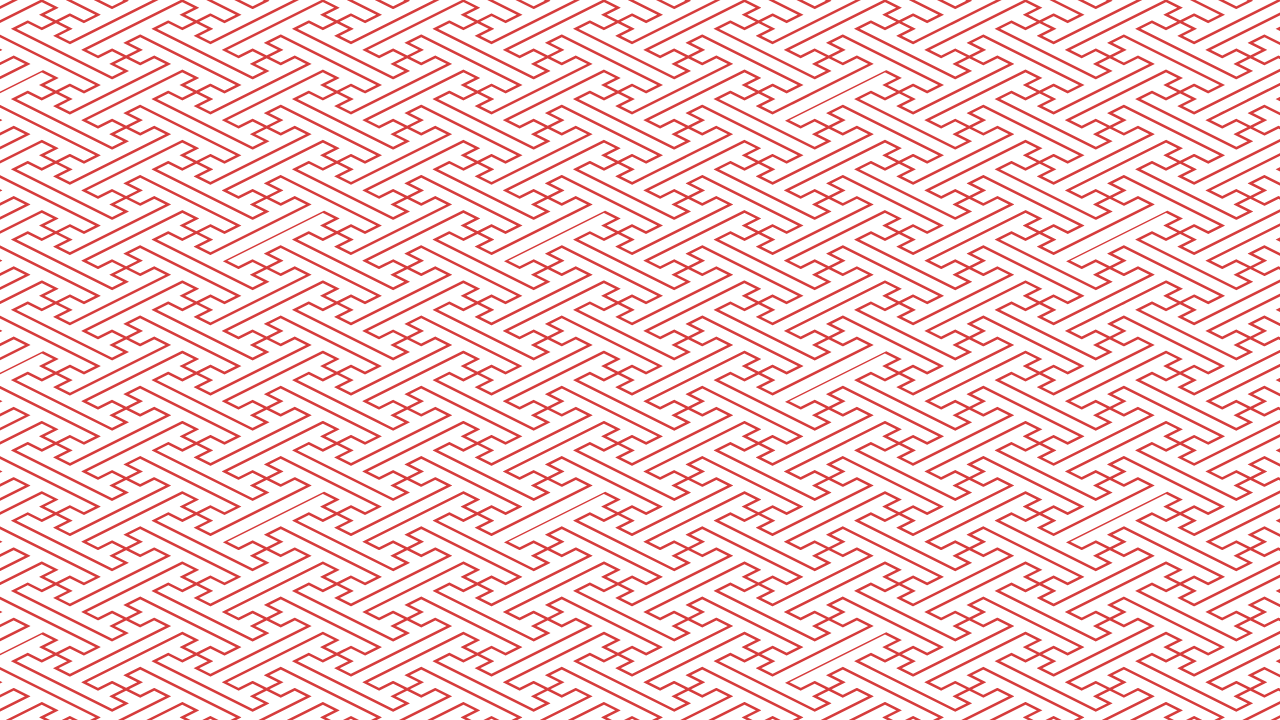◆「諸大夫」と「布衣」とは
大名や旗本は家格や役職に応じて官位を授けられ、官職に任じられることがあります。これを叙任といいます。官位とは「正四位上」「従五位下」などです。官職は「左衛門尉」や「豊前守」などです。いずれも律令制に基づく朝廷由来のものですが、江戸時代の武家官位は朝廷の官位とは別管理となっています。武家官位は権威付けのために叙任されますが、実務とは無関係です。五位の官位を「諸大夫」、六位の官位を「布衣」と呼びます。叙任されると官職名が通称とされます。上級の幕職には「諸大夫役」「布衣役」などがあります。こちらも役職一覧のページで紹介しています。諸大夫役に就任すると、多少時差はありますが、原則、叙任されます。布衣役は実際の叙任はされないようですが、幕府の儀式で一定の格式の装束の着用などが許されます。諸大夫役に就任していなくても褒賞として諸大夫に叙任されることもあります。
◆「御目見以上」と「永々御目見以上」とは
「旗本」とは、家禄が万石未満で、将軍に謁見が許される幕臣と定義されます。家禄が万石以上になると「大名」となり、将軍に謁見が許されない幕臣は「御家人」となります。この将軍に謁見が許される身分のことを「御目見以上」と呼びますが、優秀な御家人は特別に「御目見」を許され「旗本」扱いになります。ただし、原則として御目見を許されるのは一代限りです。ところが、さらに優秀な幕臣は、「布衣」や「諸大夫」となる上級職に抜擢され、子孫まで御目見が許されるようになります。この待遇のことを「永々御目見以上」と呼びます。つまり「永々御目見以上」とされて、ようやく正式に「家」が「旗本」に取り立てられたということになります。当サイトでは御家人だった幕臣が「永々御目見以上」とされた年月日が特定できれば、各旗本の役職通称遍歴の備考欄に記載しています。「永々御目見以上」記載がある人物は本人が優秀で抜擢されたことを意味します。下記に本サイトで取り上げている旗本を列挙しますので、要チェックです。