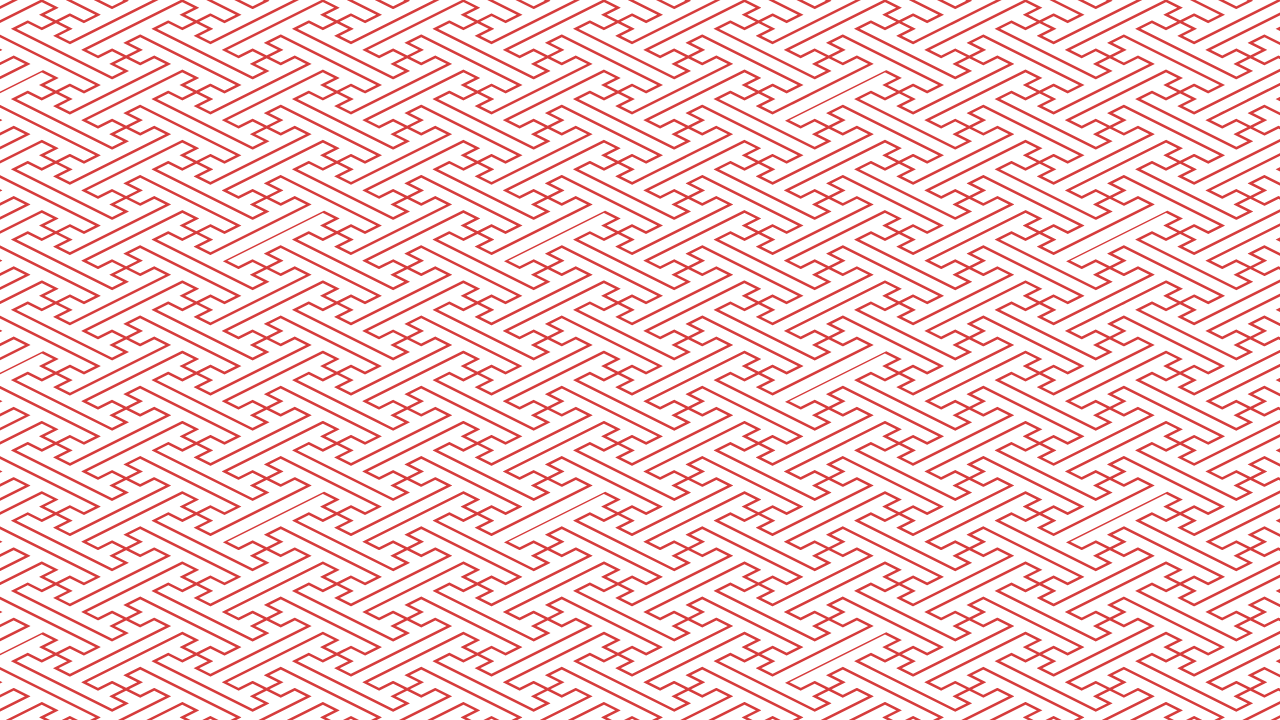◆「役高」と「足高の制」とは
「江戸町奉行」や「勘定奉行」といった役職には「役高」が定められています。主な役職の役高は役職一覧に掲載していますので、そちらをご覧ください。「役高」とはその職に就任するために必要な家禄のことです。勘定奉行であれば3000石です。ただし、そうすると高い役高の役職に就任できる者が限られてしまいます。そのため、役高に達していない家禄の者も家禄を加増して抜擢していました。ところが、家禄は代々その家に受け継がれますので、抜擢のたびに加増していると幕府の財政を圧迫してしまいます。そこで享保期に導入されたのが足高の制となります。これは家禄が役高に満たない者がその役職に就任した際は在任中に限り、役高と家禄の差分を補填支給する制度です。幕末期もこの制度が適応されています。
◆「持高」と「役料」とは
家禄が役高以上のものが役職に就任する場合は、「持高」と言って原則としては家禄の他に俸禄は支給されません。ただし、長崎奉行のような遠国奉行などは赴任するのに経費が掛かるため、家禄や役高とは別に手当てが支給されます。これを「役料」といいます。主な役職の役料も役職一覧に掲載していますので、そちらをご覧ください。役高は最高で5000石ですので、家禄5000石以上の大身の旗本になると、どの旗本職に就任しても足高は支給されません。一方、役料は家禄に関係なく支給されますので、大身の旗本にとっては役料の高い役職の方が支給額が大きくなります。