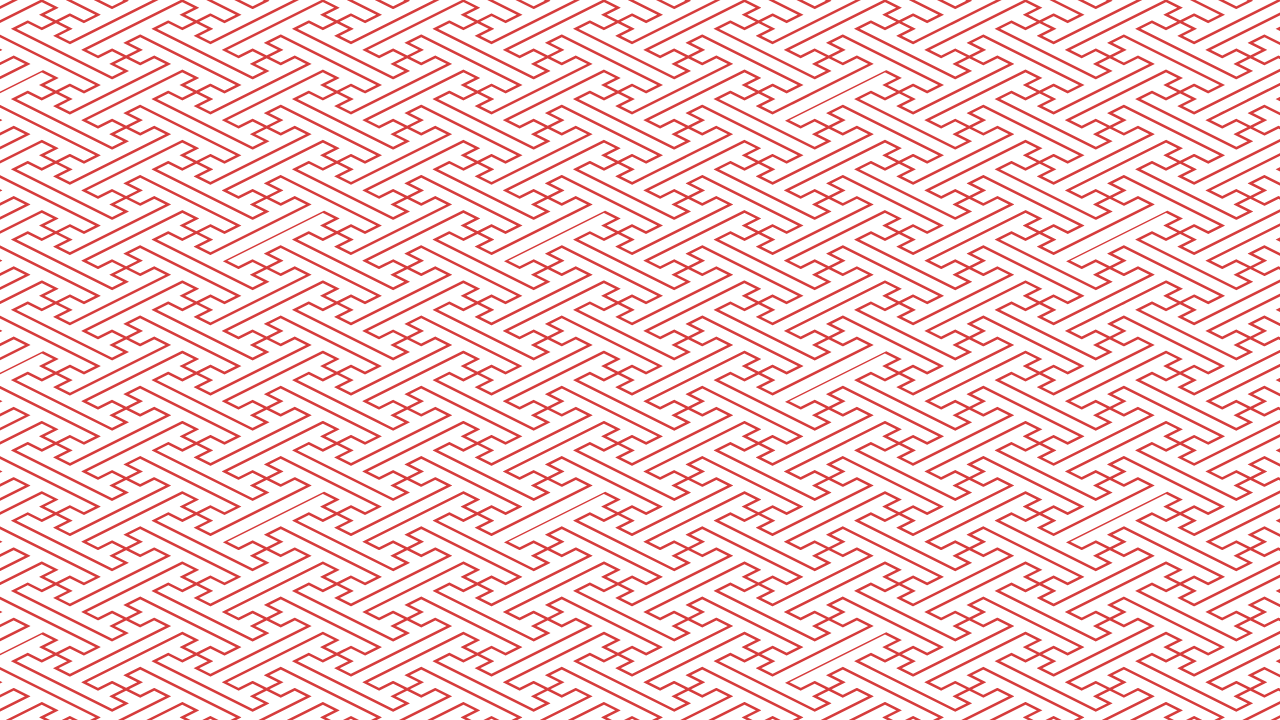◆「寄合」と「小普請」とは
旗本家は全部で5千数百家あるとされています。このうち役職についているのは6割くらいで残りの4割くらいは無役となります。無役の旗本のうち家禄が3000石以上の大身の旗本は「寄合」に、3000石未満の少禄の旗本は「小普請組」に配属されます。家禄3000石未満の旗本でも「諸大夫」や「布衣」と呼ばれる上級職の就任経験がある場合、無役となっても「寄合」入りします。これを「役寄合」といいます。また、家禄3000石の大身旗本や上級職就任者でも、懲罰として「小普請入り」させられることもあります。寄合や小普請組に配属された旗本は、役職を務めない代わりに原則として「寄合御役金」や「小普請金」を納めなければなりません。ただし、功績などを認められると無役となっても「勤仕並寄合」とされ、役職を務めているのと同様の扱いとされ、「寄合御役金」を納入しなくてもよいとされました。
◆「寄合肝煎」「火事場見廻」「中川番」とは
「寄合」は無役ではありますが、寄合衆の世話役的な立場である「寄合肝煎」が「寄合」のなかから任じられます。「寄合肝煎」は「寄合衆」が就くべき幕職に欠員が出た際に、後任について推薦を求められたりしましたので、寄合衆の人となりを把握するために会合したりしていました。また大概順などに入っていないため、正式な幕職ではないですが、寄合衆が担った役職に「火事場見廻」や「中川番」などがありました。「火事場見廻」は文字通り火事が起こると現場の見廻りを「使番」などとともに担いました。そのため「使番」が兼帯することもありました。「火事場見廻」をへて「火消役」に就任する寄合もいます。また「中川番」は本所深川にある「中川船番所」を管轄する役目で、やはり寄合衆が担当しました。