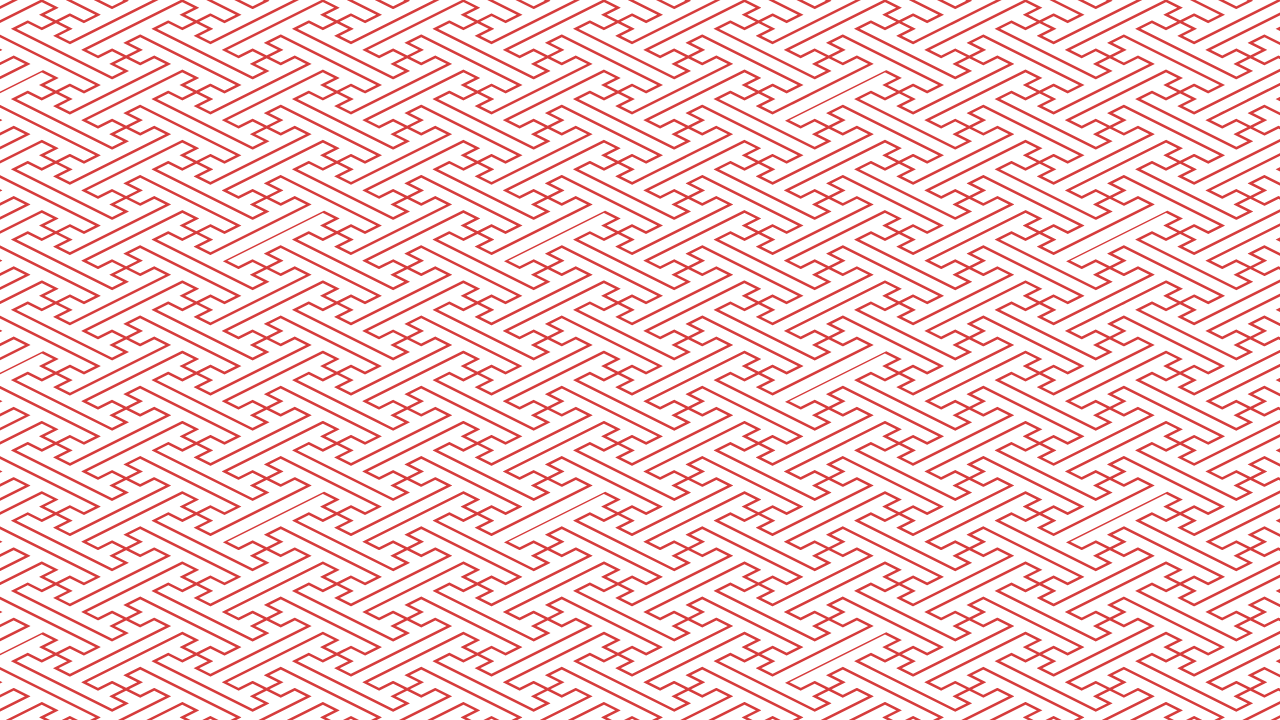◆「家禄」とは
「家禄」とは大名・旗本・御家人の「家」に代々受け継がれていく俸禄のことです。家禄は役職につかなくても支給されますが、有事の際に動員される義務が課せられます。そのための武芸を磨いたり、武具の手入れをしたり、防御施設の修繕をしたりといった準備をしておく必要があります。家禄は武士の家に支給されますので、その家で「家督」を継いだ当主にのみ支給されます。旗本の俸禄はこの「家禄」がベースになります。ここに就任する役職によって別途俸禄が追加されます。
◆「知行取」と「蔵米取(切米取)」とは
家禄の支給の方法は主に「知行取」と「蔵米取(切米取)」の2パターンがあります。まず「知行取」は「知行地」と呼ばれる領地が与えられ、年貢を徴収することで俸禄を得ます。知行地の収量を500石などと表します。一方「蔵米取(切米取)」は、玄米が幕府の蔵から直接支給されます。支給される蔵米(切米)の量を500俵などと表します。1石は約2.5俵にあたりますが、知行取の場合、知行地の収量のうちの約4割を年貢として徴収するので、500石の知行取の手取りは結果的に500俵くらいになるとされています。ただし、知行取は「領主」であるのに対して、蔵米取(切米取)は雇われの身ということで、知行取の方が格式が高いとされています。蔵米取には〇人扶持などと表記されることもあります。これは〇人の食い扶持として一人当たり1日5合が支給されるという意味で1人扶持はおよそ5俵に相当するとされています。