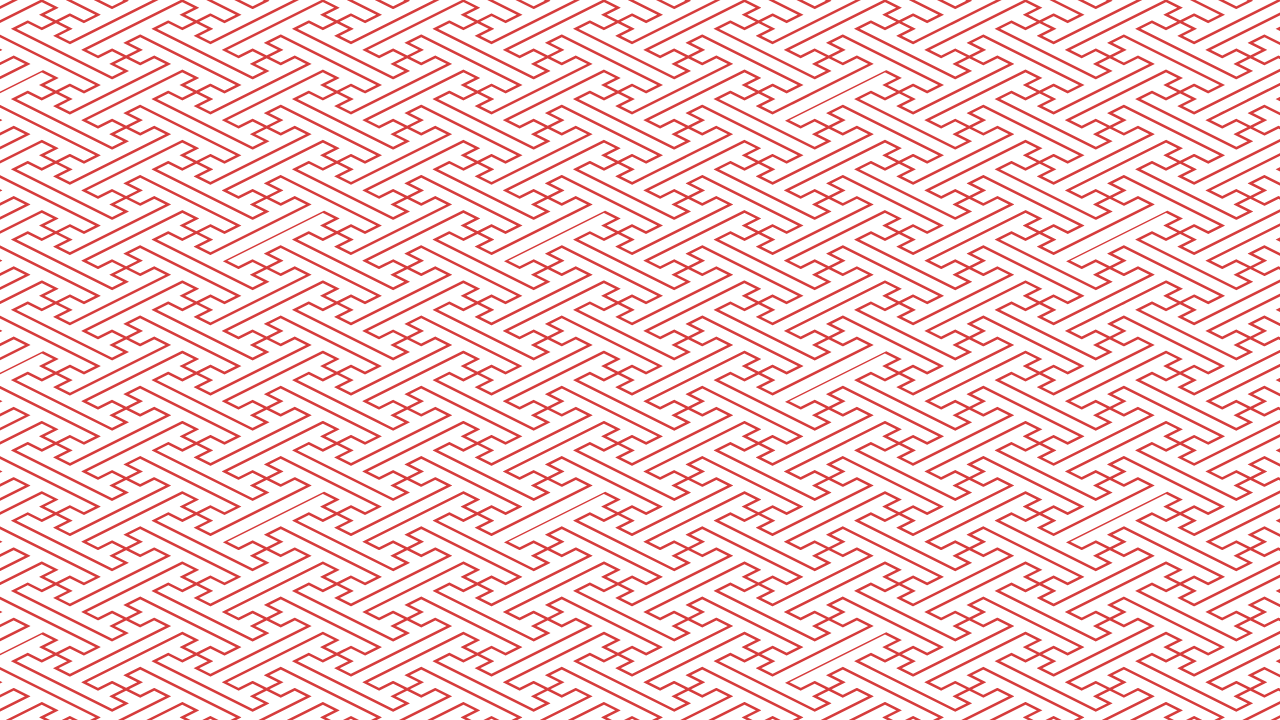◆「家督」と「惣領」とは
武家は「家督」を継いだ当主がその家を次代に継承していく責任があります。後継がいないまま、当主が死亡したりすると原則、その家は改易となります。そのため「惣領(大名は嫡子)」と呼ばれる次期当主を決めておかなければなりません。実子に適当な人物がいない場合は、養子を迎えてでも家を存続させる必要があります。幕職には原則として各家の家督を継承した当主が就任しますが、学問などの才を買われて、惣領の時点で幕職に抜擢されることがあります。惣領には家禄が支給されませんので、こういった場合、当主の家禄とは別に幕府から蔵米(切米)が支給されます。惣領には屋敷地は与えられず、当主の屋敷に部屋住みをしています。部屋住惣領などとも呼ばれます。
◆「嫡孫承祖」とは
実子や養子が家督を継ぐ前に死亡してしまうなどの事情で、当主の孫が「家督」を継承することがあります。これを「嫡孫承祖」と呼びます。箱館奉行など務めた堀利煕は家督を継ぐ前に外交交渉の責任を取って万延元年に切腹してしまいますが、当時の堀家の当主は利煕の父の堀利堅でした。堀利堅は文久2年に自身の孫で、堀利煕の子である堀利孟に家督を譲りますが、この家督相続は「嫡孫承祖」の実例となります。堀利煕は外交分野で活躍する旗本ですが、家督を継ぐことがなく果ててしまったため、『江戸切絵図』には屋敷地の記載が確認できません。