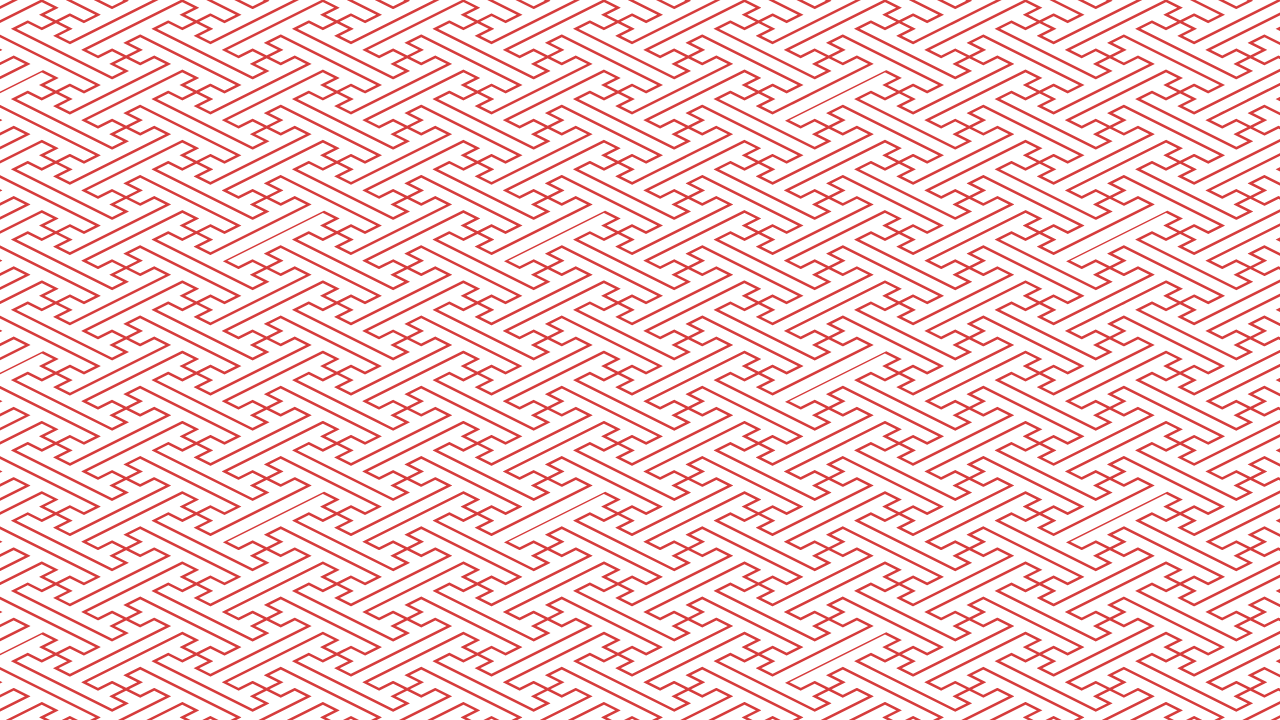◆大名に準じた特別な旗本
「高家」とは別の形で特別な待遇を受けた旗本の家格に「交代寄合」があります。「交代寄合」とは文字通り「参勤交代」をする「寄合」という意味です。一般の旗本は知行地を与えられている旗本でも「定府」や「在府」と言って、江戸屋敷に居を構えますが、「交代寄合」と呼ばれる旗本家は、多くの大名と同様に知行地と江戸屋敷の間で参勤交代をしていました。一般の旗本が若年寄支配なのに対して、「交代寄合」は大名と同様の「老中支配」です。また、一般の旗本が就く役職にはほとんど就かず、大番頭、講武所奉行、陸軍奉行といった大名旗本混在職に就任する「交代寄合」が稀に確認できます。
◆「表御礼衆」「四衆」とは
「交代寄合」の中でも「表御礼衆」と呼ばれる19家が将軍への謁見の仕方などでも優遇され格式が高く、「四衆(那須衆、美濃衆、信濃伊那衆、三河衆」と呼ばれる要衝の地の防衛を担うとされる12家が次に家格が高く、「四衆」に準ずる「交代寄合」として「米良家」「岩松家」があります(家数はいずれも幕末期の数)。「表御礼衆」は1家を除いて家禄は3000石を超え文字通り「寄合」と言えますが、「四衆」では家禄3000石を超える家は那須衆の3家に留まり、「米良家」は無高(ただし5000石格扱い)、岩松家は120石と小禄の家もあります。最上家、山名家、生駒家、金森家や豊臣秀吉麾下で活躍した竹中家、平野家など名門の武家の流れをくむ家が選ばれています。『武鑑』での表記も「表御礼衆」に限っては大名に準じた表記となっており、一般の旗本に比して詳細な記述として大名に準ずる待遇を表現していると思われます。