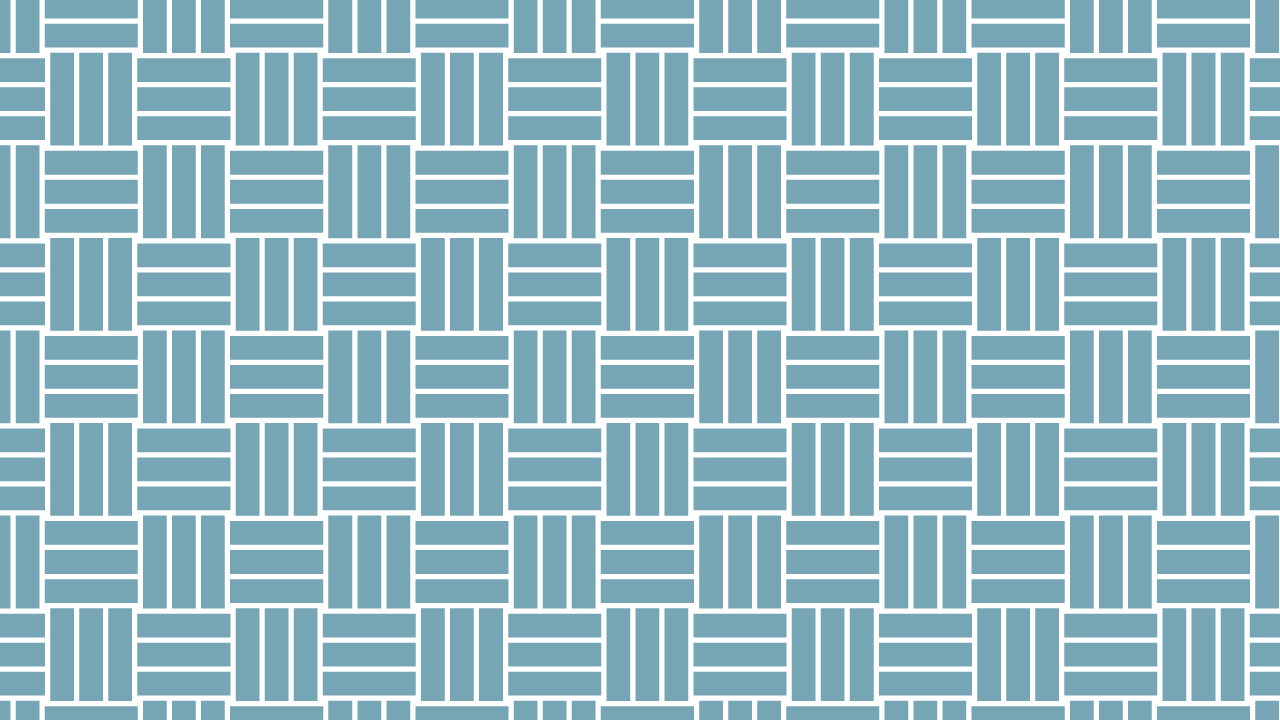明治33年に発刊された『幕末政治家』(著:福地桜痴)の中に『幕末の有司』と題する章が設けられています。その中で幕末の旗本について論じられています。当サイトで取り扱う人物が数多く言及されていますので、下記に全文を紹介します。
『幕末の有司』(著:福地桜痴)
幕府の末路に當り、幕閣に座して政権を執れる閣老、若くは闇外に在りて大政に參與せる有數政治家の行為に付ては、概畧已に叙述したり。是を外にして大諸侯には初に松平薩摩守(齊彬)ありて阿部内閣を助けたる事あり。次に松平土佐守(容堂)松平阿波守(阿州) 伊達遠江守(宇和島)および上杉池田(因州)の諸公ありて松平越前守(春嶽)と與に會合して一團結の状を為し、堀田内閣の時に當りては外交議及び儲君議に關して勢力を爲したり。終に會津桑名ありて、幕府と其運命を供にしたり。
又幕府の重職にて、閣老には、眞田信濃守、久世大和守、間部下総守、諏訪因幡守、小笠原壹岐守、阿部豊後守、松平伊豆守の如き、多少みな直接に幕政を左右したるの跡あり、酒井若狹守(京都所司代)松平大和守(總裁)酒井雅樂頭(大老)これ亦然りとす。 其餘若年寄、大阪御城代、或は溜詰等の地位に在りて幕政に關係したる諸侯、一々に之を數へ来れば、指を幾十人の多きに屈せざるを得す。是等の諸人、其智愚腎不肖は措て言はず、閣外に在るものは、往々閣議の為に阻まれて其志を展ふる事を得ず、閣中に列する者と雖ども、或は群議に制せられ、或は事情に牽肘せられて、其思ふ所を達するを能はずして、空しく時事を慨嘆に附去れり。有爲の器にして尚且然り、況や凡庸の材たるに於てをや。是を要するに幕府の末路に際し、眞の政治家たるの識量膽畧を具備して、政局の難關に當るの手腕ある大器は、曾て一人も幕閣に其人なかりしと云ふに外ならざるのみ。
幕府二百餘年、泰平の結果として、政治上の機關は自から備はりて運轉し、加ふる諸事槪皆格式慣例に由りて擧行し、敢て之に違ふ事を許さざりしを以て、苟も普通の智識を有するの諸侯なれば、誰を擧て閣老に任するも、優に其職を奉するに足れり、假令菽麦を辨せざる紈袴子弟をして、内閣に列せしむるも、其破綻を現はす程の事はあらずして以て嘉永の年末に至れり。然るに米國より彼理(ペリー)を派遣して江戸灣に来らしめ、露國よりは布恬廷(プチャーチン)を全権として長崎に至らしめてより、幕閣は眞の政治家を必要とするに迫り、不十分ながらも、阿部伊勢守その地位に立たるなり。
扨嘗時幕府の制度として、國家の大事を處決するの重要議に與るものは闇老にして、參政(若年寄)これが補翼たり。世間にては御老中若年寄と並べ稱して、倶に今日の内閣員の如くに思做せども、原来參政(若年寄)は閣老(御老中)の如く權威を有する者に非ず、抑々幕府の制度は軍國制度にして、閣老は將軍家の執權にて、諸大名に指揮命令を下すの職權を有すれども、參政は單に旗本を指揮するに止まりて、諸大名に及ぼすの職権を有せざるなり。去れば之に附屬する監察の如きも、大目付は大名目付にて、御目付は即ち旗本目付と唱へたるなり。此制度を諸般の政治に應用したるが故に、三奉行芙蓉の間の重職は皆閣老に隷し諸衛士および其他は参政に屬する事となりぬ。而して此重職中にて、尤も政治に與るは寺社奉行、町奉行、御勘定奉行(これ三奉行なり)大目付、御目付にて凡を重大の裁判を爲し及び大事を議する、必らず此三奉行両目付に諮詢して、其意見を聞くを例とす(但し此三奉行両目付を五手と名け、評定所一座と唱ふるは、斷訟の場合に限るなり) 此中にも御勘定奉行には公事方(裁判) 御勝手方(會計)の二局に分れ、公事方は斷訟に限れども、御勝手方は啻に會計のみならず。都て百般の政治に於て、御目付と與に閣老の顧問となり、補佐となりて之を翼賛するが故に、現に阿部閣老が外使来朝の時に當り、尤も其意見を問ひて、親密に内議したるは、御勘定奉行と、御目付なりけり(寺社奉行、町奉行、大目付等には表面の内議に及びたるだけにて、親密の内議には與からしめず) 故に當時藤田東湖が烈公に對して答へたる如く幕政の實権は閣老と御勘定奉行御目付および奥御右筆組頭(内閣書記官長の如き職)との間にありと云へるも決て誤見には非ざるなり。夫もその筈の事よ幕府の重職は、旗本門閥の出身にて、自から門地に限ありて、誰は番頭の家なり、誰は御番士の家なりと定まりて、敢て異常格外の登庸を爲さざるが中にて、獨り御勘定奉行のみは、民間の事情に通するの材を要するを以て、御勘定奉行定員五名の中には、必らず一名若くは二名の登庸せられたる人あるを例とす(例は御普請役より支配勘定—御勘定—御勘定組頭―御勘定吟役と成りて御勘定奉行御勝手方に昇るが如き。又は御小人目付より御徒目付―御勘定評定所留役―同組頭―御勘定吟味役―御勘定奉行公用方に昇るが如き是なり)既に幕末に有名なる御勘定奉行の川路左衛門尉、井上信濃守、竹內下野守等は皆御普請役の輕輩より次第に昇進して、遂に御勘定奉行に登庸せられたる人々なり。又御目付の如きは、従来人材登庸の地にして、旗本中の青年にて才學の令名あるものは、或は昌平學校の及第に依り、或は長官の推薦によりて御番士に擧られ或は將軍家の近侍に選ばれ、其中より再び抜擢して御使番に試み(又は試る事なくして)御目付に任せらゝるを常として、又稀には他の小吏より漸次昇進して御目付に昇るもありたるなれば、同じく人材の淵叢とは認められたり。然らば則ち阿部閣老が、従来の慣例に則とりて、専ら御勘定奉行と御目付に重を置き、是に内議したるは、決して法外の事には非ざりき。
嘉永六年六月久里濱に於て彼理(ペリー)に面會して書翰を請取たるは、戸田伊豆守 井戸石見守にて、両人とも浦賀奉行なり、是は彼理(ペリー)が軍艦を初に入したるは浦賀なりけるを以て、其地の奉行たるに付き、其任に當りたるなり、而して此井戸は初め鐵太郎と呼びて、御目付出身の人なり。
次で阿部内閣は海防掛の一局を開きて、凡そ幕府有司中の器量ある輩を入らしめたり、其重立たるは石河土佐守(御勘定奉行) 松平河内守(御勘定奉行) 川路左衛門尉(御勘定奉行) 筒井肥前守(大目付前長崎奉行) 伊澤美作守(大目付前長崎奉行)鵜殿民部少輔 (御目付)堀織部正(御目付)大久保左近將監(御目付) 永井玄蕃頭(御目付) 岩瀬肥後守 (御目付)江川太郎左衛門(御代官)の諸人にして、外交の大事は専ら此海防掛の衆評にて決せられたるが如し。此海防掛は右の如き諸奉行両目付より出て組織したる事務局なりければ、其の屬官は御勘定奉行又は御目付の隷屬たる御勘定、御徒目付、御小人目付の小吏を以て是に任じたれば、御徒目付には平山謙次郎(後に圖書頭外國奉行若年寄)柴田貞太郎(後に日向守外國奉行)永持亭次郎等の如き御勘定には竹内清太郎(後に下野守御勘定奉行) 中村爲彌(後に出羽守下田奉行)等の如き皆その屬官となりて、多少各自の意見を吐きて其長官を補翼したり。此海防掛は後に外國應接掛となり、更に名称を更めて、外國奉行と成りて外務の局を開くに至れり。
然るに東西外交の應接に其人を選ふに當り、米國の方は井戸石見守(大目付) 井戸對馬守(町奉行)林大學頭(御儒者)鵜殿民部少輔(御目付)伊澤美作守(浦賀奉行)戸田伊豆守(浦賀奉行)の諸人をして横濱に於て彼理(ペリー)に應接せしめ、露國の方は筒井肥前守(大目付)川路左衛門尉(御勘定奉行)古賀謹一郎(御儒者)水野筑後守(長崎奉行)永井玄蕃頭(御目付)の諸人をして長崎に於て布恬廷(プチャーチン)に應接せしめたるに、此委員の中に林古賀等の儒官を加へたるは敢て人才と云ふが故に非ず。朝鮮信使來聘の如き、琉球人来朝の如き、外交上の禮典には儒官これに與ると従来幕府の慣例たるを以て、米露の應接にも之を加へられたるなり。
是よりして幕府の滅亡に至るまで、幕府の有司にして、閣老を翼賛したる人物は、随分其數ありて、政治家と稱するに足るべきもの尠しとせず、試に其二三を擧れば松平河內守、川路左衛門尉、水野筑後守、大久保越中守(一翁)、岩瀬肥後守、永井玄蕃頭、堀織部正、小栗上野介、勝安房守、江川太郎左衛門、向山榮五郎等數十人に降らざるへし。其遭際は各々殊なりて、成敗みな同じからずと雖ども、其中にて水野筑後守、岩瀬肥後守、小栗上野介の三人は、特に一際勝れたる人物にて、名けて幕末の三傑と云はんも、敢て過稱には非ざるが如し、是は余が一個の私評のみに非ず、栗本鋤雲、朝比奈閑水の諸老も、亦常に此言を爲せるにて、之を知るに足るべきなり。