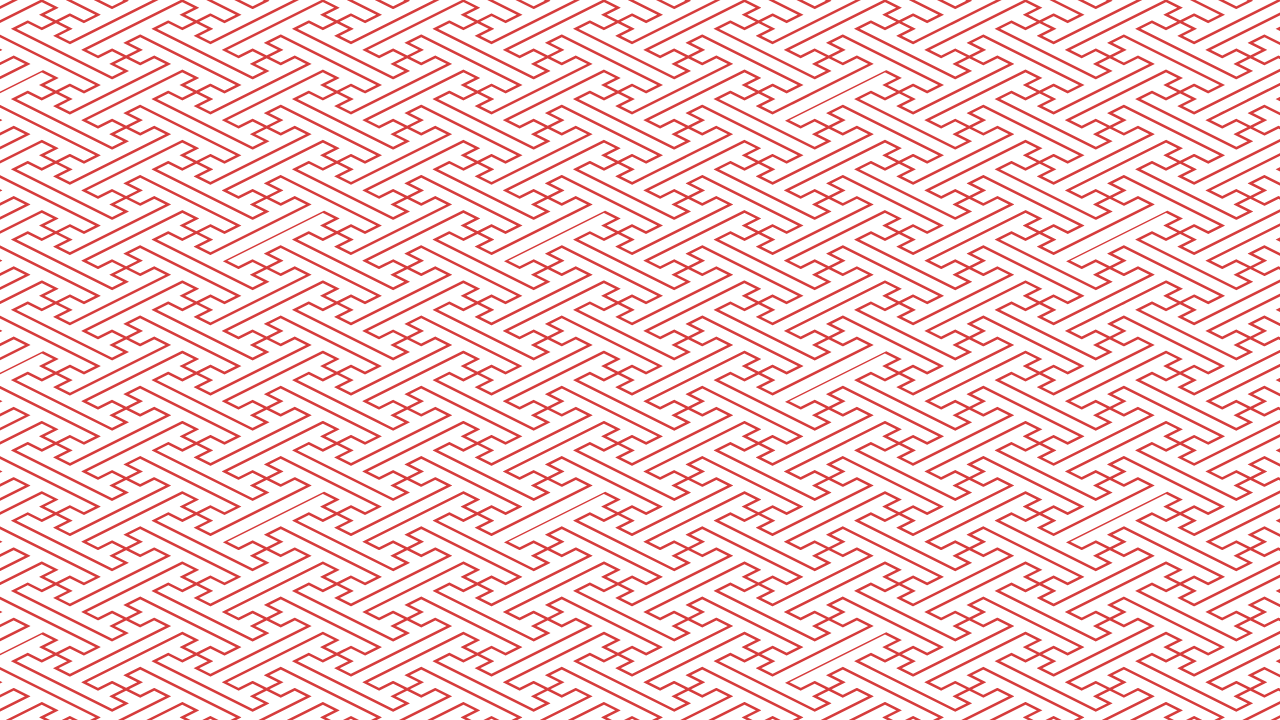◆将軍家と「御三家」「御三卿」について
『江戸切絵図』を見ていると、なんと「松平〇〇」と表記される区画が多いことか。これが屋敷地を推定する際に実に厄介です。「松平家」とは家康が「徳川」と改名する前に名乗っていた家名です。江戸時代の「松平家」を簡単に説明すると「将軍家および徳川家の親戚筋の家名」なのですが、厳密にみるといくつかのパターンがあります。これらの「松平家」を見ていく前に、まず「徳川家」について確認します。幕末期に「徳川家」を名乗ったのは、徳川将軍家と御三家(尾張徳川家、紀州徳川家、水戸徳川家)、御三卿(田安徳川家、一橋徳川家、清水徳川家)の7家となります。御三家、御三卿は、将軍の兄弟から分かれた家で将軍家に後嗣がない場合、後嗣を出す資格を有する家として「徳川家」の名乗りを許されていました。ただし、『江戸切絵図』ではこれらの家の屋敷地について、「尾張殿」や「一橋殿」などと表記され、「徳川家」表記の屋敷地は確認できません。
◆「御家門」と「御連枝」について
将軍家の親戚筋でも「松平家」は将軍後嗣を出す資格は有しません。将軍の兄弟から分かれた家でも一度他家を継いでいる家は「御家門の松平家」を名乗りました。この将軍の兄弟から分かれた「御家門の松平家」には越前松平家、会津松平家、越智松平家があります。また、家康の母の於大の方が再婚先の久松家で生んだ「家康の異母弟たち」が松平家を称することを許され、久松松平家となります。さらに、長篠の合戦の功績で家康の長女の婿となった奥平家に生まれた「家康の外孫」も松平家を称することを許され、奥平松平家となります。この2家も「御家門の松平家」とされています。「御家門の松平家」のうち、越前松平家には分家が多く存在し、福井松平家、雲州松平家、結城松平家、明石松平家、津山松平家など大名だけでも8家あります。また、久松松平家も発足時から3家存在していますし、幕末期には4家の大名家と多く旗本家が存在しています。また、御三家も家の存続のために複数の分家を成立させていきます。こちらは「御連枝」といいますが、将軍継嗣の資格がない親戚筋ということからやはり「松平家」を名乗ります。尾張徳川家の御連枝には大窪松平家、四谷松平家、大田窪松平家。紀州徳川家の御連枝には西条松平家、高森松平家、葛野松平家、鷹司松平家。水戸徳川家の御連枝には高松松平家、森山松平家、石岡松平家、宍戸松平家があります。
◆「庶流の松平家」について
「御家門」「御連枝」はいずれも江戸時代に分かれれた文字通り徳川将軍家の親戚筋の家として原則、親藩とされます(久松松平家、奥平松平家の一部に譜代とされる家も存在します)。一方、徳川家康が三河の大名となる前から既に「家康を出した松平家」とは別に存在していた「松平家」も数多くあります。これらの家も広い意味では将軍家の親戚筋には違いありませんが、血統的にも遠縁ですし、家康による開幕までのいずれかのタイミングで臣従しており、徳川家の家臣、つまり酒井家や本多家などと同様に、譜代として扱われます。これらの松平家は「庶流の松平家」とされますが、『寛政重修諸家譜』に記載がある以下の14家が代表的です。竹谷松平家、形原松平家、大草松平家、五井松平家、深溝松平家、能見松平家、長沢松平家、大給松平家、滝脇松平家、福釜松平家、桜井松平家、東条松平家、藤井松平家、三木松平家。また、このほかにも大河内松平家や世良田松平家なども「庶流の松平家」とされます。これらの庶流「松平家」の中からは大名家となっている家もありますが、多くの旗本家を排出しています。これらの「庶流の松平家」に対して、のちに将軍家として「嫡流の松平家」的存在となる松平家を「安祥松平家」と言ったりもします。
◆褒美の称号としての「松平家」
「御家門」「御連枝」「庶流」はいずれも将軍家の親戚筋に違いありませんが、功績のあった大名などに対して「親戚同様の待遇」をするという意味合いで、特別に「松平」の名乗りを許されていた家が外様大名、譜代大名に存在します。外様大名では前田家、島津家、毛利家、伊達家、池田家、鍋島家、黒田家、浅野家、蜂須賀家、山内家の10家となります。このうち前田家、池田家、浅野家は分家の一部も含めて松平の名乗りを許されていました。譜代大名では、本庄家、松井家、戸田家、柳澤家などがあります。『江戸切絵図』においては、これらの家の屋敷地も原則「松平〇〇」と表記されます。これまで見てきた様々な「松平家」が入り乱れて、『江戸切絵図』にはやたらと「松平家」がみられるようになっています。