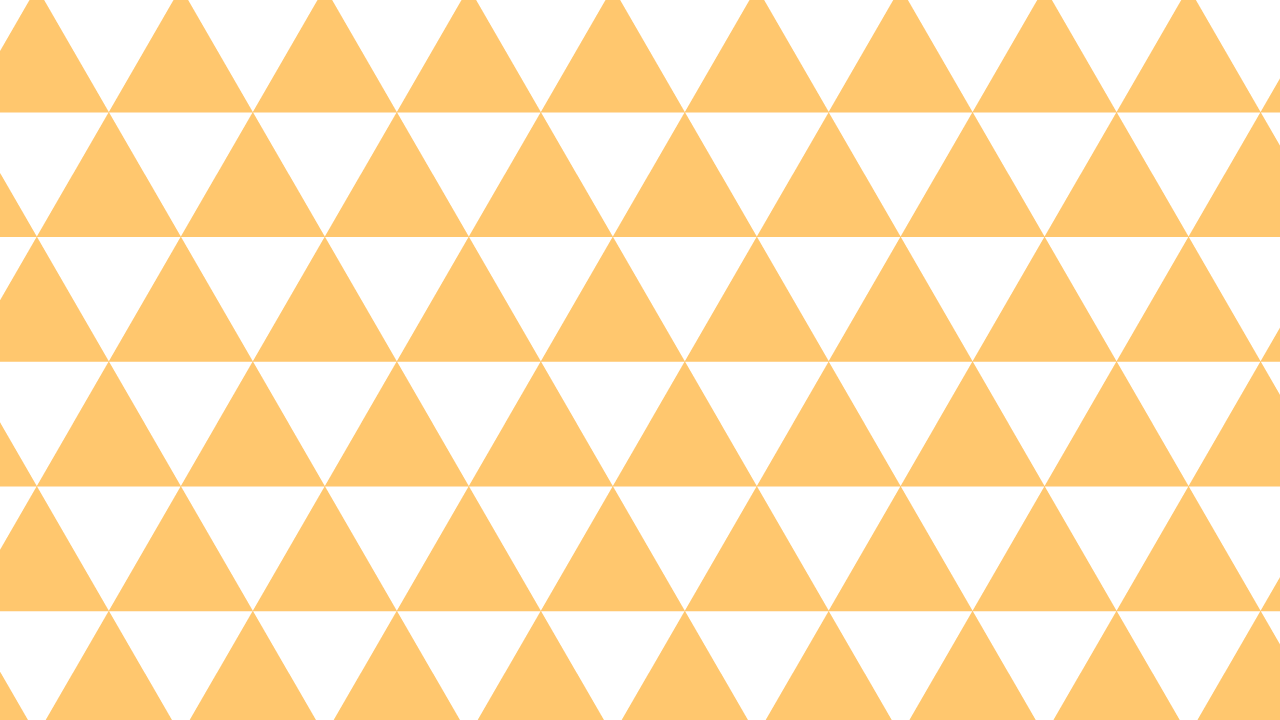一般の「旗本」は領地をもつ「知行取」でも在府(江戸在住)で若年寄支配です。ところが「交代寄合」と呼ばれる旗本は、家禄は万石未満であるため「旗本」であるにもかかわらず、知行地の陣屋に在陣し、参勤交代で定期的に江戸に参じ、将軍に謁見し、支配は老中で、江戸城内の伺候席(詰所)は帝鑑間や柳間となります。これらはいずれも大名と同様の扱いとなっています。
このような大名のような旗本がなぜ設けられたかについては、大坂の陣の際に、交通の要衝に比較的大身の旗本を配置し大坂方への備えとしたことが起源という説が有力です。要衝の備えという役目柄、在府ではなく、知行地陣屋での在陣が基本となったようです。
「交代寄合」の中にも「表御礼衆」「四衆」及び「四衆」に準ずる家(岩松家、米良家など)が存在します。「表御礼衆」は大名と同様に表御殿での将軍謁見が許された最も家格の高い「交代寄合」で、幕末期には20家が存在ました。「四衆」は「那須衆」「美濃衆」「伊那衆」「三河衆」を構成する12家の総称で、将軍謁見は旗本と同様に廊下にて行われました。
「表御礼衆」は稀に、大名や旗本が就く幕職に就任しましたが、「四衆」はほとんど幕職に就くことはありませんでした。『武鑑』での記載方法も「表御礼衆」は大名に準ずる大きな扱いですが、「四衆」は旗本のなかでも「寄合」に近く、「諱(いみな)」の表記もない扱いで、「岩松家」は「表高家」と同様に「名字、通称、本姓、諱」の表記となっています。「米良家」は『武鑑』に表記が確認できません。
表御礼衆
菅沼家 菅沼定志 菅沼盈志 菅沼盈冨
久松松平家 松平康豊 松平康正
竹谷松平家 松平清倫 松平敬信
榊原家 榊原照砥
本堂家 本堂親道 本堂親久
生駒家 生駒親道 生駒親敬
山名家 山名義問
池田家(松平姓) 松平喜道
平野家 平野長発 平野長裕
木下家 木下俊國 木下俊清
山崎家 山崎治正
最上家 最上義偆 最上義連
戸川家 戸川達敏
溝口家 溝口直景
朽木家 朽木大綱 朽木之綱
近藤家 近藤用明 近藤用吉
金森家 金森近義 金森近明
五島家 五島盛貫
伊東家 伊東祐膺
四衆
<那須衆>
那須家
福原家
芦野家
大田原家
<美濃衆>
高木家(西家)
高木家(東家)
高木家(北家)
<伊那衆>
知久家
小笠原家
座光寺家
<三河衆>
松平家(拳母)
中島家
その他
岩松家
米良家